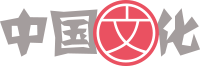中国語テキスト
企者不久,跨者不行,自见不明,自是不彰,自伐无功,自矜不长。
其在道,曰余食赘行,物或有恶之,故有道不处。
翻訳
つま先立ちする者は長く立っていられない;大きな歩幅で歩く者は歩けない。
自分の見解に固執する者は明らかでない。
自分を認める者は輝かない。
自慢する者は功績がない。
自らを誇る者は長く続かない。
道の観点からこの行為を判断すると、残り物や醜いこぶのように、人々に常に嫌悪を抱かせる。
だから、道を持つ者はこれに執着しない。
注釈
つま先立ちする者は遠くを見ようとする;大きな歩幅で歩く者は速く進もうとする。この二つの譬えは、自分を高めようとする者が長く続かないことを示している。
この章は前章の続きである。議論を好む者が長く続かないように、つま先立ちしたり大きな歩幅で歩く者も長く立っていられず、長く歩けない。著者はこれにより、自分の知恵で勝とうとする者の過ちを浮き彫りにしようとしている。
つま先立ちする者は他人より頭一つ上になろうとするだけで、長く立っていられないことを知らない。大きな歩幅で歩く者は他人を追い越そうとするだけで、長く歩けないことを知らない。
著者は後に述べる公理を証明するために、理解しやすい譬えを使っている。
彼は帝国の他の人々が自分に及ばないと思い込んでいる。そのため、彼らの資質や才能を活かすことができない。だから明らかでない(自见不明 )。
自分を認める者(他人を非難する者)は、他の人々は自分ほど能力がないと思い込んでいる。そのため、彼らの才能を活かすことができない。だから輝かない(自是不彰 )。
自分の功績を自慢する者は、まだ人々に認められ評価されていないことを恐れているが、人々は逆に彼を軽蔑する。だから功績がない(または功績を失う)(自伐无功 )。
自らを誇る者(自分の能力を誇示する者)は、他の人々は自分に及ばないと思い込んでいる(自矜 )。
そのような人々は他人を打ち負かすことを好む。功績を得るどころか、むしろ早く死を招く(不长 )。
余食赘行 という言葉は释德清 の説明に基づいて翻訳した:「行」(歩く、または行動する)は、「形」「体」と読むべきである。古代、この二つの言葉は互いに使われていた。この読み方はコメント者Cによっても推奨されている:「残り物(余食 )や体のこぶ(赘行 )のように」。これらは人々が嫌悪するものである(残り物とこぶは人々が嫌うものである)。
第4章の二番目の文で、河上公 は「或」(もしかすると、誰か)を「常に」と訳している。
道を持つ人は謙虚を保つ;必然的に老子 が非難するこのような行為に執着しない(従わない)。